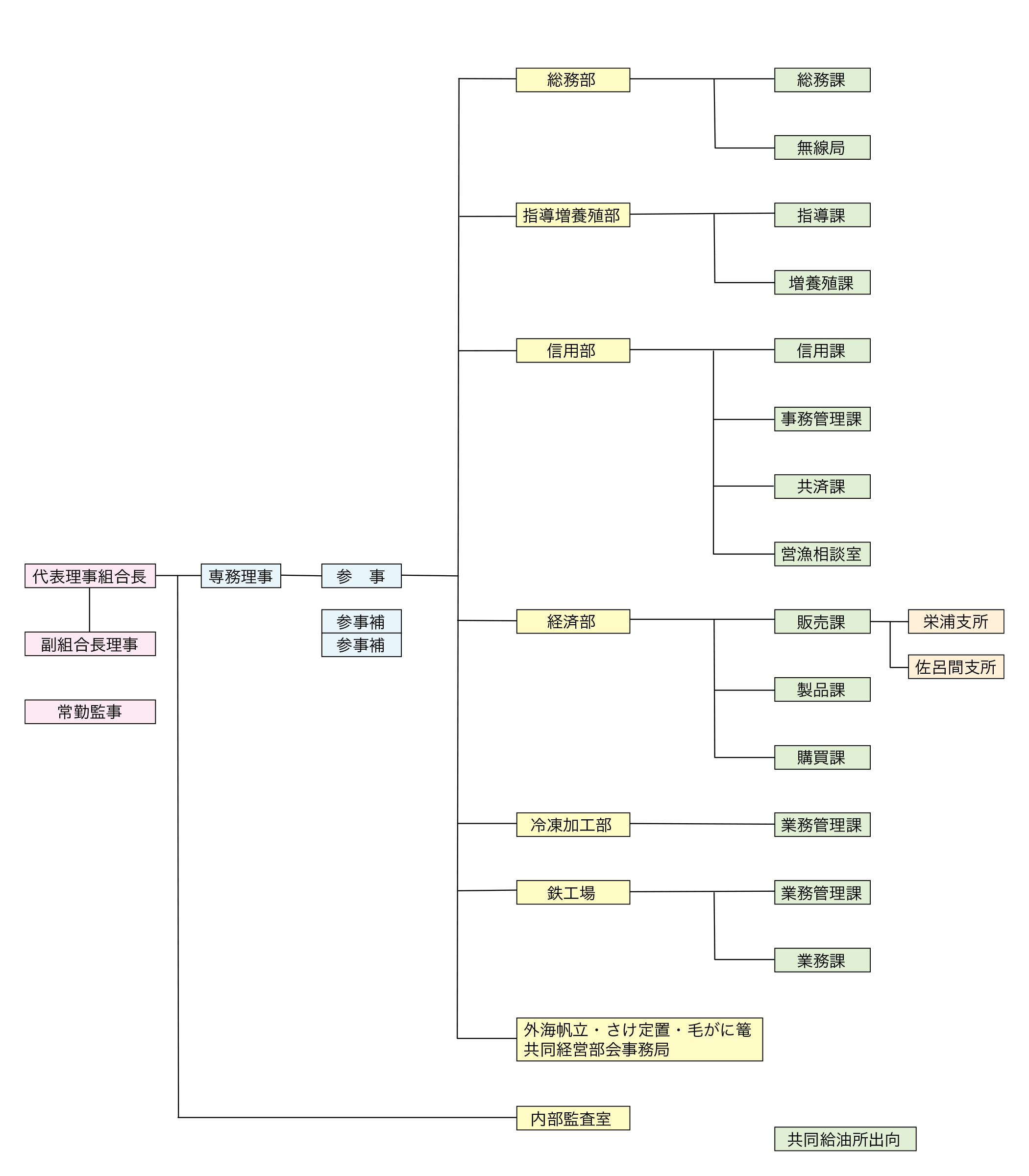ごあいさつ
本組合の主力漁業である外海帆立漁業は、明治45年鐺沸(とうふつ)漁業協同組合(本組合の前身)創立以来、豊漁と不漁・禁漁を繰り返して参りましたが、その間の長い経験から、組合員による帆立稚貝の採苗、中間育成技術の研究と適正放流、漁場区画割による漁獲方法(四輪採制)の導入、全組合員による共同経営等により“獲る漁業”から“育てる漁業”へと転換を図り、昭和54年より安定的漁業に成長し、現在に至っております。
この間の歴史は、先人達のたゆまぬ努力によって築き上げられたものであり、私達はその相互扶助の精神を基調として今後の漁業経営を策定して参ります。
漁業環境は国内外で厳しさを増しておりますが、国民の食生活の一翼を担う立場を認識し、協同組合運動の中で漁業者はもとより、豊かな地域社会の建設に邁進していく所存であります。
今後とも皆様のご支援を賜りますようお願い致します。
常呂漁業協同組合
代表理事組合長 吉田 恭